ペン習字をやっていても気が抜けると元のくせ字に戻ってしまうことがあります。
きれいな字を書くためには
「すき間を等間隔にしよう」
「横画を伏せるようにふっくら書こう」
「全体のバランスを考えて文字列が曲がらないように文章を揃えて書こう」
など、たくさんのことを意識し続けなければいけません。
字を書くことはとても頭を使う作業です。
そんなことから、きれいな字を書けるようになるためには、ある程度脳の仕組みを理解しておくことも必要なのかもしれないと思い、今回、脳の機能と書字の関係について、色々調べてみることにしました。
読み書きに必要な脳の機能
 |
| 脳のイメージ |
人間の脳には様々な機能を司ってる領域が点在しており、例えば脳の前方部分(前頭前野)には言葉を話す能力を司る[ブローカ野]、脳の側方部分(側頭葉)には言葉を理解する能力を司る[ウェルニッケ野]があることなどが知られています。
では、文字を書いたり読んだりする能力は脳のどの部分が司っているのかというと、[ブローカ野]や[ウェルニッケ野]のような特定の領域はなく、脳内のあらゆる領域が総合的に使われます。
私たちが文字を目にした時、目から入ってきた情報はまず脳の後方部分(後頭葉)にある[視覚野]に送られ、そこから脳の上部(頭頂葉)にある連合野を介して言語情報へ変換され、その情報がさらに[ウェルニッケ野][ブローカ野]に送られることで意味を理解し、文字を読むことができます。
そして、字を書く時には「一画目をどこに配置しようか」や、一画目を上手く書けなかった場合「次の二画目でどのようにバランスを調整しようか」など[空間認知力]を働かせ、お手本の字と自分が書いた字の違いをよく観察するために[注意力]を働かせます。
他にも、例えば字を覚える時、私たちは単に視覚情報だけに頼って学習しているわけではなく、鉛筆で何度も書くことを繰り返し、書く時の手の動き(ストローク)も体性感覚や身体運動と結びつけて学習しています。
これには身体運動を司る[運動野][線条体][小脳]、感覚情報を司る[体性感覚野]、感覚情報を統合する[頭頂連合野]などが機能しています。
そして、きれいな字の形を覚えるために[記憶力]も働かせています。
※【脳トレ書道のススメ】参照
少し調べただけで読み書きに必要な脳の機能がたくさん見つかりました。
普通、ペン習字をやる時に脳の機能なんて考えないと思いますが、こういったことを知っておくことで、自分がやっている練習を客観的に振り返ったり、必要であれば練習内容を修正したりできるようになるのではないかと思います。
今回はこの中から特にペン習字と関係が深そうな「注意力」と「記憶力」についてさらに深掘りしていきたいと思います。
書字に影響を与える脳の機能「注意力」
まずは注意力について。
注意力には4つの要素があります
持続性
一つのことを集中して続ける力
持続性がない例→練習に集中できずすぐに飽きてしまう
転導性
別のことに意識を移す力
転導性が高すぎる例→周りのことに気が散りやすく書字に集中できない
選択性
周りの多くの刺激から、ある刺激を引き出す力
選択性が低い例→複数の文字の中からある文字を見つけるのに時間がかかる
分配性
複数のことへ同時に意識を向ける力
分配性が低い例→文字の大きさや配置を調整する場面など、複数のことを同時に考えなければいけない状況でうまく対応できない
注意力には上記4つの要素がありますが、ペン習字では文字の形や大きさなど、細かいことをたくさん、また同時に意識しないといけないので、4つの中でも特に分配性の注意力(複数のことに同時に注意を向ける力)が課題になりそうです。
参考ポスト↓
#一文字入魂
— 桐敷たかを@文字年齢5才 (@takaobiisiki) December 15, 2019
んー
なぜたった一文字をちゃんと書けない。
縦画は3分の1から。頭をしっかり出す。
偏は右を揃える。縦画より内側に収める。払いの足元を揃える。などどこかの意識が抜けたり、線が曲がったり、バランスが崩れたり。
合格点は出せないけどこれが今の精一杯。
早く上手くなりたい。 pic.twitter.com/64RFEr8S4S
上記のポストのように
「縦画は頭をしっかり出す」
「横画と交わる位置は横画右側1/3のところ」
「偏は右を揃える」
「払いの足元を揃える」
など、これら全てに注意をはらおうとするとキャパオーバーでテンパってしまい、
「縦画で頭をしっかり出す」の意識が抜ける
などの現象が起こります。
同時に複数のポイントに意識を向けて字を書くことは、それだけで分配性の注意力を要求される課題であり、脳のトレーニングにもなります。
書字の学習過程を運動学習の段階で考える
先ほどの項目でも説明しましたが、私たちは字の形を覚えるとき、ノートなどに繰り返し反復練習をすることで、手の動き(ストローク)も体性感覚や身体運動と結びつけて学習しています。
そこで、書字学習を運動学習の理論に当てはめて考えてみたいのですが、アメリカの心理学者ポール・フィッツは技術を習得する工程には「認知段階」「連合段階」「自動化段階」の3つに分けられると述べています。
認知段階
学習の初期段階で目標や注意点を一つ一つ言語化しながら反復練習している段階。脳内では前頭前野や前帯状皮質といった「注意」「意識」など高次な働きに関わる部位が活発に働いている。
連合段階
意識に頼った初期段階を徐々に脱していく段階。自分の動きを客観的に判断しながら修正や微調整が可能となる(「何をするのか?」という意識が「どのように行うか」という意識に変わっていく)
自動化段階
脳内に運動プログラムが書き込まれた状態。高度な技術も半ば反射のように迅速に実行できるようになる。脳内では運動野、基底核、小脳などの活動が活発になる。
運動学習はこのような段階を経て行われます。
この理論を先程の「校」のポストに当てはめて考えると
「縦画は頭をしっかり出す」
「横画と交わる位置は横画右側1/3のところ」
「偏は右を揃える」
この3つでキャパオーバーになっていた当時の状態は、運動学習の初期「認知段階」に当たるのではないか?
だとすれば、学習が「自動化段階」まで進んだ時、これらは無意識に行えるようになり(脳内に空きスペースができ)、キャパオーバーも改善されるのではないか?
と考えられます。
そうすれば脳内の空いたスペースを利用して、今度は「払いの足元を揃える」にも意識を向けられるようになるはずです。
このポストを投稿したのは2019年ですが、2025年の今、改めて振り返ってみると、確かに上記で考察した通りのことが起きています。
ペン習字を始めた頃(2019年)と現在(2025年)の比較
当時のポストと同じ「校」を書いて比べてみました。
 |
| ペン習字を始めた頃(2019年) ポイントを意識し過ぎてキャパオーバーになっていた |
 |
| 現在(2025年) ほとんど意識しなくてもこのぐらいの字が書けています |
記事の冒頭で「気が抜けると元のくせ字に戻ってしまう」という例を挙げましたが、練習を継続し、学習が自動化の段階まで進むと、それほど意識しなくてもある程度の字が書けているような気がします。
書字に影響を与える脳の機能「記憶力」
ちなみに上記で説明した「運動学習」という概念は、脳の機能である「記憶力」という観点からも説明することができます。
記憶は大きく「感覚記憶」「短期記憶」「長期記憶」の3種類に分類されます。
感覚記憶
視覚・聴覚など五感からの情報がそのまま保持されるだけの記憶。保持時間はほんの数秒程度。
短期記憶
脳内に入力した情報をごく短時間だけ保存し、その情報を元に思考・計算・判断などの作業を行う。いわゆるワーキングメモリーがこれにあたり、情報処理が終わるとすぐにその情報は消去され、また別の情報が上書きされていく。保持時間は数秒から数分ぐらい。
長期記憶
長期記憶は言語化できる「陳述記憶」、言語化できない「非陳述記憶」の2つに分類される。さらに「陳述記憶」は体験やできごとについての「エピソード記憶」、言葉や意味などの知識に関する「意味記憶」に分類される。「非陳述記憶」は動作に関する「手続き記憶」、先に受けた刺激から影響を受ける「プライミング効果」、情報を関連付けて反応が起こる「条件付け」、刺激に慣れることで感覚が変化する「非連合学習」に分類される。
長期記憶の保持時間は数日、数ヶ月、一生続く記憶もあり、定期的に思い出す機会をもつことで保持時間を延長することができる。
 |
| 長期記憶の分類 |
※【記憶はスキル】参照
記憶だけでもたくさん種類がありますが、この中で特にペン習字に影響すると考えられるのは短期記憶に分類される「ワーキングメモリ」と長期記憶に分類される「手続き記憶」です。
ワーキングメモリと手続き記憶
ワーキングメモリ
ワーキングメモリとは脳の作業スペースと言われています。
書き順を覚えるなど、書字の学習でもワーキングメモリはフル活用されます。
ワーキングメモリが大きい人(脳内の作業スペースが大きい人)は、そうでない人と比べて初めから多くの美文字ルールを頭に入れることができるので、ペン習字の学習スピードも速くなると考えられます。
ワーキングメモリが小さい人は一つの学習が自動化の段階に達してから(脳内に新たな情報を入れるスペースができてから)、また新しい美文字ルールを追加するという手順で段階を踏んでいくことになるため、ワーキングメモリが大きい人と比べて学習のスピードは遅くなることが考えられます。
手続き記憶
手続き記憶は大脳基底核や小脳を中心とした神経回路に記憶されている「動作に関する記憶」(暗黙知)です。
私たちが慣れ親しんだ行為や動作をする時、いちいち言葉にしなくてもそれが可能なのは、その行為や動作が手続き記憶として定着しているためです。
この記憶は何度も体の筋肉を動かして、繰り返し練習することで身に付きます。
ペン習字を継続していると、学んだ記憶がワーキングメモリ(短期記憶)→意味記憶(言語化された長期記憶)→手続き記憶(体の動きとして覚えている長期記憶)と置き換わっていきますが、この手続き記憶に置き換わった状態を、運動学習の視点から説明すると「自動化段階」(意識せずに書ける段階)ということになります。
ペン習字は記憶力もフル活用する作業と言えそうです。
まとめ
今回、脳の機能とペン習字の関係について、様々な書籍を参考にして深掘りしていきました。
私なりに内容を整理すると
・字を書くことは脳のあらゆる領域をフル活用するので脳トレになる
・練習を継続していると学習した内容が自動化され、きれいな字を書くことに対する負担感が軽減してくる
・ペン字学習は練習の過程で美文字理論を意味記憶から手続き記憶へ置き換えて定着させていく作業であり、記憶を意識した学習が上達のカギになる(お手本を見なくても書けるようになることを意識して練習する)
という感じになります。
ちなみに手続き記憶は長期記憶に分類されているので、一度覚えると忘れにくいという特徴があります。
このレベルまで記憶を定着させることができれば、仮にしばらく練習ができない状態になったとしても、能力をある程度維持することができそうです。
無意識に手が動くようになるまで、根気強く練習していきたいですね。
それでは今回はこの辺で。
最後までお読みいただきありがとうございました。
その他参考文献

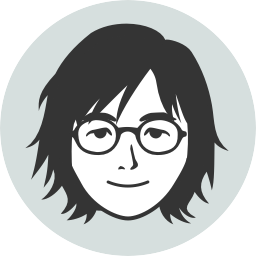
0 件のコメント:
コメントを投稿